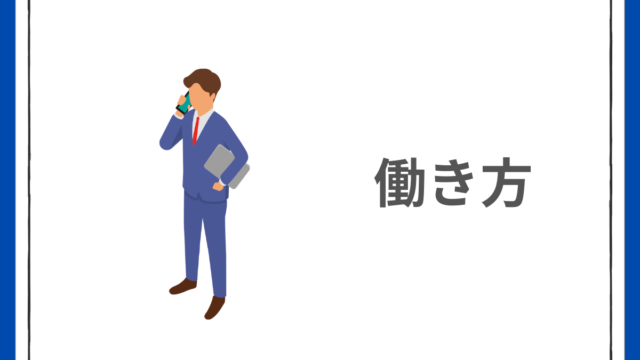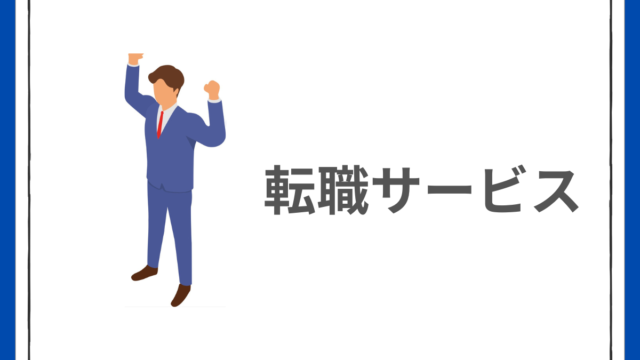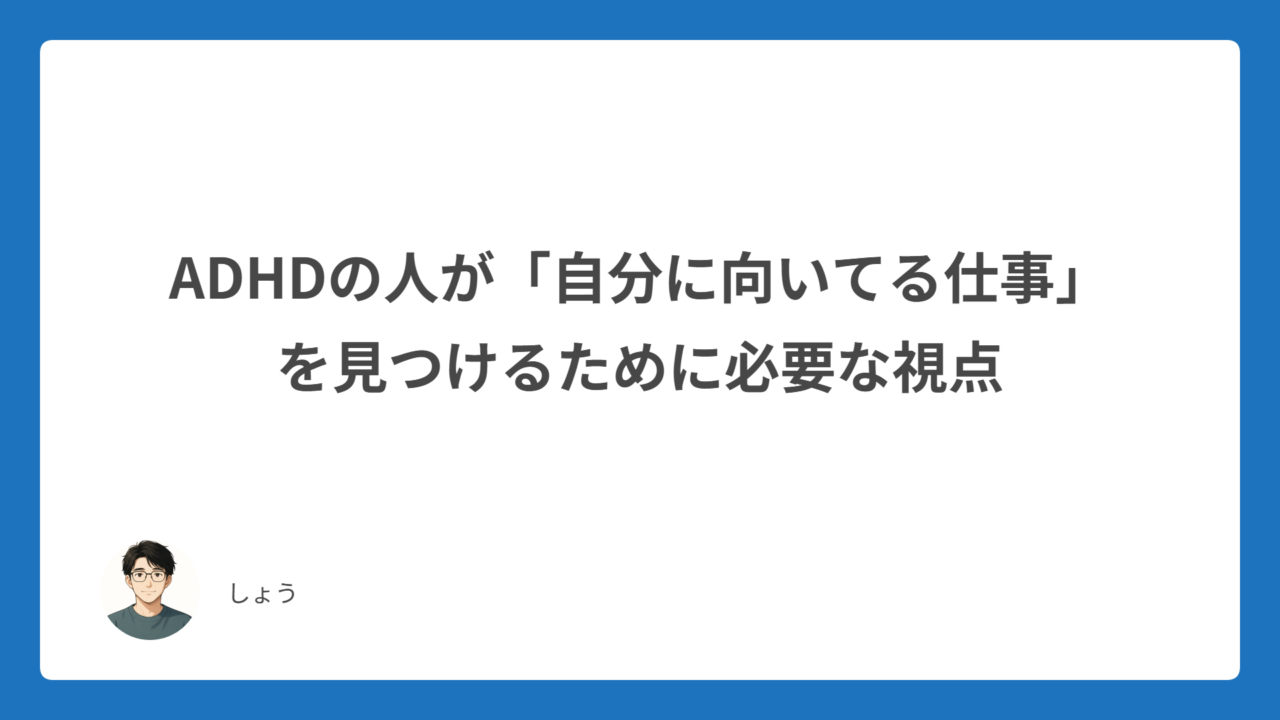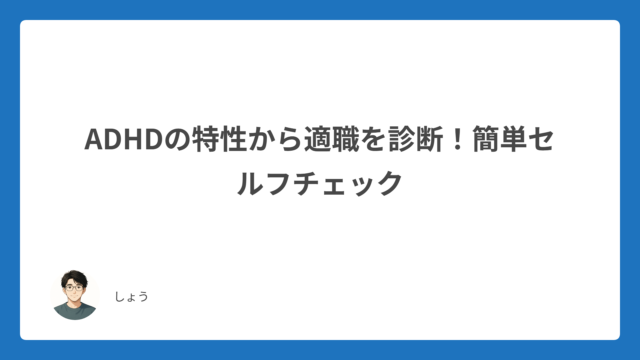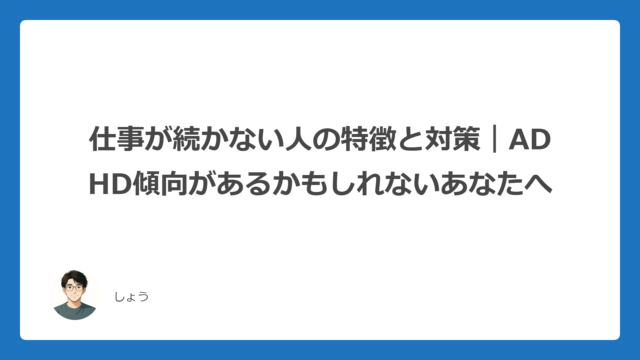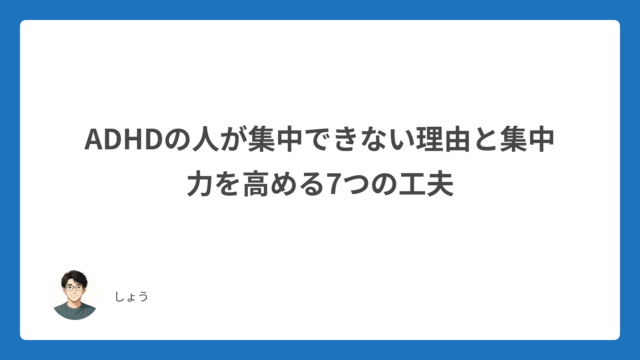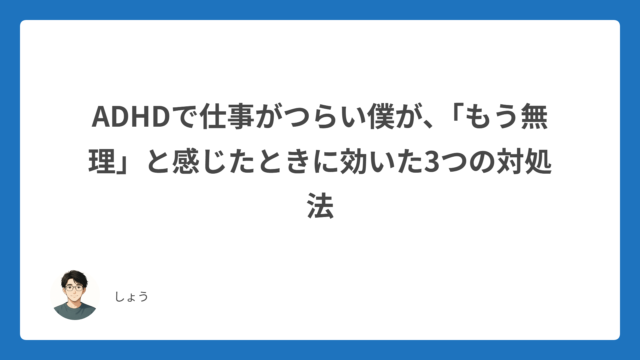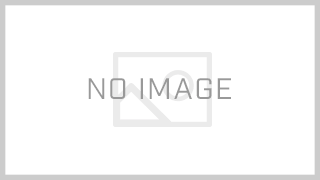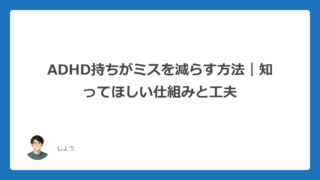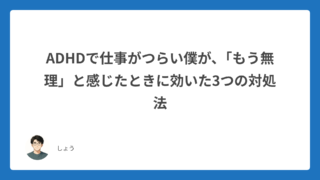こんにちは、当ブログを運営しているしょうです。
私は会社員として10年以上働いてきましたが、「人よりミスが多い」「仕事が続かない」「評価されない」と感じる場面が何度もありました。
精神科で相談した際には「ADHD傾向があるかもしれない」と言われ、自分でも「どうしてうまく働けないんだろう」と悩んできた一人です。
そんな僕でも、「合う仕事」に出会えたことで、少しずつ働き方や気持ちが変わっていきました。
この記事では、ADHD傾向のある人が“自分に向いてる仕事”を見つけて就職するための視点を、実例と共に5つの切り口で解説していきます。
この記事を書いている人
- 発達グレー×仕事・転職
- ADHD気質あり/働き方に悩んできた会社員
- 働き方を見直してWeb広告プランナーに転職
- 悩みながらも、マネージャー職に
- 仕組みと工夫で年収650万円
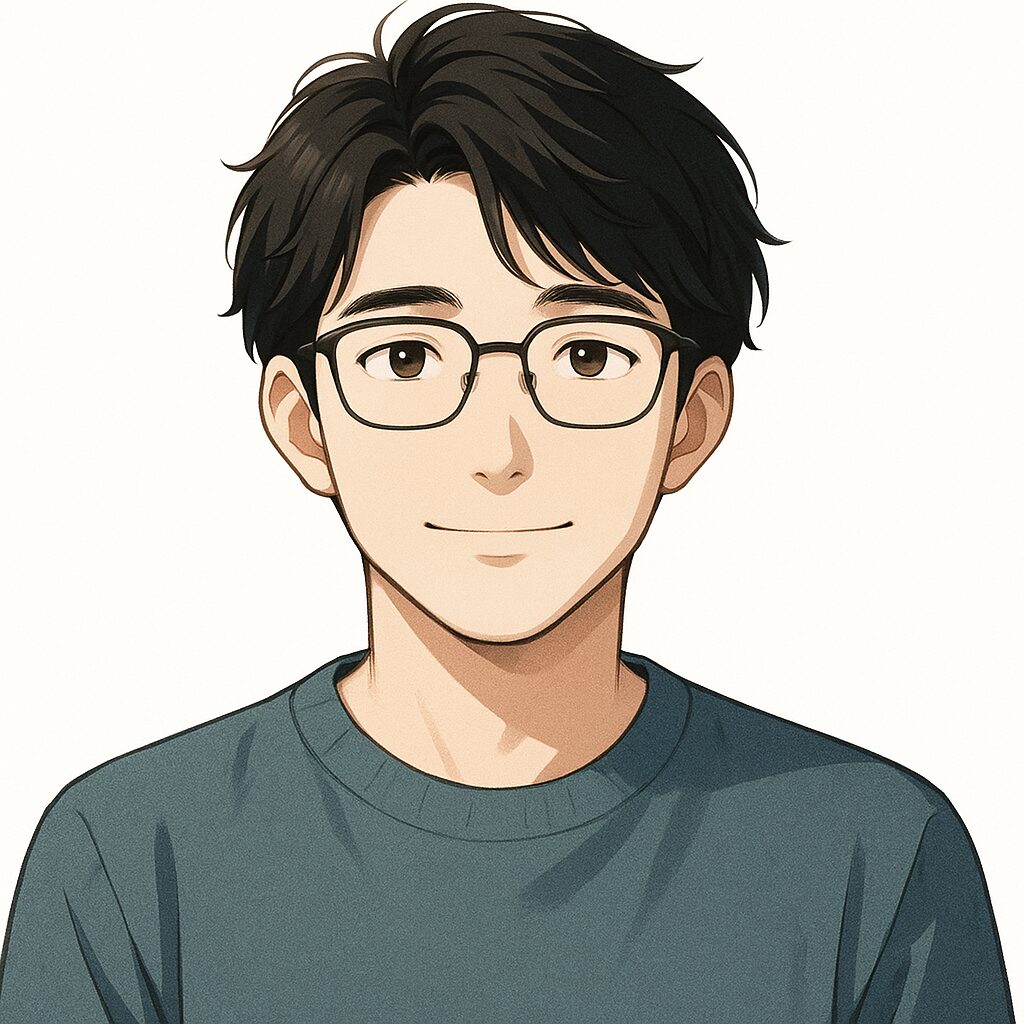
rtoc_mokuji
ADHDでの就職は「工夫」と「理解」がカギになる
ADHDの特性を持つ人は、仕事において以下のような課題を抱えやすいです:
- タスクの抜け漏れや優先順位の混乱
- 人間関係でのストレスや空気の読み合い
- 時間管理が苦手で遅刻・遅延が起きやすい
- 指示が曖昧だと動きにくい/過集中で疲れやすい
でもこれは「ダメな人間だから」ではありません。
特性に合った環境と、ちょっとした工夫やサポートがあれば、ADHDの人でも自分らしく働くことができます。
ADHD就職の成功例に学ぶ5つの視点
① 自己理解と自己分析がすべての土台
「どんな仕事が合うか」を考えるには、まず**「自分の特性」を知ること**が必要です。
自己理解のためにやってみたいこと:
- 過去の仕事で「しんどかったこと」「うまくいったこと」を紙に書き出す
- 自分が自然に集中できた作業や、飽きずに続けられたことを思い出す
- 周囲の人に「自分の強み・弱み」を聞いてみる
たとえば、**「ルールが曖昧だと混乱する」**という特性があるなら、
マニュアルや業務フローがしっかりしている職場が向いている可能性が高いです。
このように、自分の「苦手」と「得意」が整理できると、求人選びや面接でも迷いが減っていきます。
② 自分の特性が活かせる職場・職種を選ぶ
ADHD傾向がある人は、以下のような職場・職種で力を発揮しやすいと言われています:
- クリエイティブ系(デザイン、動画編集、ライティングなど)
- 営業系(特に興味ある分野)
- 企画・マーケティング職
- 研究職や技術系職種(集中力や探究心を活かせる)
ポイント:「自分がストレスなく取り組める要素があるか?」を基準に見ること。
また、発達特性に理解のある職場(障害者雇用や発達支援実績のある企業)を選ぶことで、長く働ける環境を作りやすくなります。
③ サポートや工夫を“遠慮なく使う”
ADHDの人が「ひとりで全部やろう」とすると、準備・管理・対人対応でパンクしやすくなります。
だからこそ、利用できるサポートは、積極的に頼ることが重要です。
使えるサポートの例:
- 就労移行支援(面接練習・仕事体験・職場定着支援)
- 転職エージェント(発達特性に理解のある担当者を選ぶ)
- 障害者雇用枠(配慮や制度が明文化されている)
- 職場での「声かけ」や「タスクの見える化」の相談
また、ツール面でも以下のような工夫が有効です:
- Googleカレンダーで締切管理&通知
- ToDoリストアプリ(Todoist/タスクペディアなど)
- ルーティンをスマホのアラームで補助
④ 悩みを抱え込まず、早めに相談する
就職後、「あれ、思ってたのと違う」「つらいけど言えない」と感じる場面は誰にでもあります。
ADHDの人は特に、我慢し続けて突然辞めてしまうというパターンに陥りやすいため、早めの相談が大切です。
相談できる相手例:
- 職場の上司や人事(配慮を求める/働き方を調整)
- 就労支援員やカウンセラー(客観的に状況を整理)
- 家族や信頼できる友人
「迷惑をかけたくない」と思いがちですが、周囲は意外と“言ってくれた方が助かる”と感じています。
⑤ 働き始めてからも“定着支援”を続ける
「就職がゴール」ではありません。
実際には、就職後の半年〜1年で辞めてしまう人が多いのが現実です。
だからこそ、就職後も以下のような“定着の工夫”があると安心です:
- 定期的な面談(不安や課題を共有)
- 業務の棚卸しと、やることの整理
- 月に1回は「仕事以外の自分」を回復する時間を確保
- カウンセリングや外部支援機関との継続的な関わり
少しずつ慣れていく中で、自分なりのリズムや働き方が作れるようになります
まとめ|「向いてる仕事」は、特性と環境で決まる
ADHD傾向のある人にとって、就職は「不安」と「希望」が混在するイベントです。
でも、以下の5つの視点を意識すれば、“自分らしく働ける場所”を見つけることは十分可能です:
- 自己理解と自己分析がすべての土台
- 特性が活かせる職場・職種を選ぶ
- サポートやツールを“遠慮なく使う”
- 困ったら早めに相談するクセをつける
- 働き始めてからも“定着の工夫”を続ける
今日から早速初めていきましょう